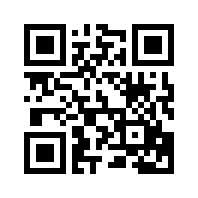こんにちは。フォービックの出原廣太です。
アベノミクスの金融緩和政策によって、市場は急激な円安が進みました。
政策の是非論はさておき、輸出企業にとっては競争力が増すことは間違いありません。
したがって輸出関連企業においては軒並み株高の様相です。
輸入企業にとっては、コストが数か月で20%も上昇するという事態に直面しています。
卸売業で90%の原価、小売業で80%の原価と、製造業で70%の原価と仮定すると、
今回の急激な円高は、企業の利益率を確実に圧縮させると思われます。
企業は年度変わりの月に値上げを通すべく躍起になっています。
しかし、日本の国内産業は多段階制に商社、問屋、卸、小売りなどと
それらのコストを皆で吸収し合う傾向にありそれぞれが苦しい状況に変わりないでしょう。
当社は木材製品の輸入商社です。
円安局面の他にコスト上げ要因もあるのでレポートしておきたいと思います。
アメリカの景気が上向いていることで、南米の材料が高騰しています。
具体的にはラジアータパインが際立っています。
隣の消費大国 中国で比較的安価で供給の安定したラジアータパインの
消費量が増えているのは、東南アジアのゴム(ラバーウッド)の
価格が上がったことが要因だと思われます。
円安、株高のもたらすムードが盛り上がるなかで、円安以外のコスト高
要因にあまり気づいていないという印象をうけますが、
世界的な景気の変動による材料価格の動向に注意しなければなりません。